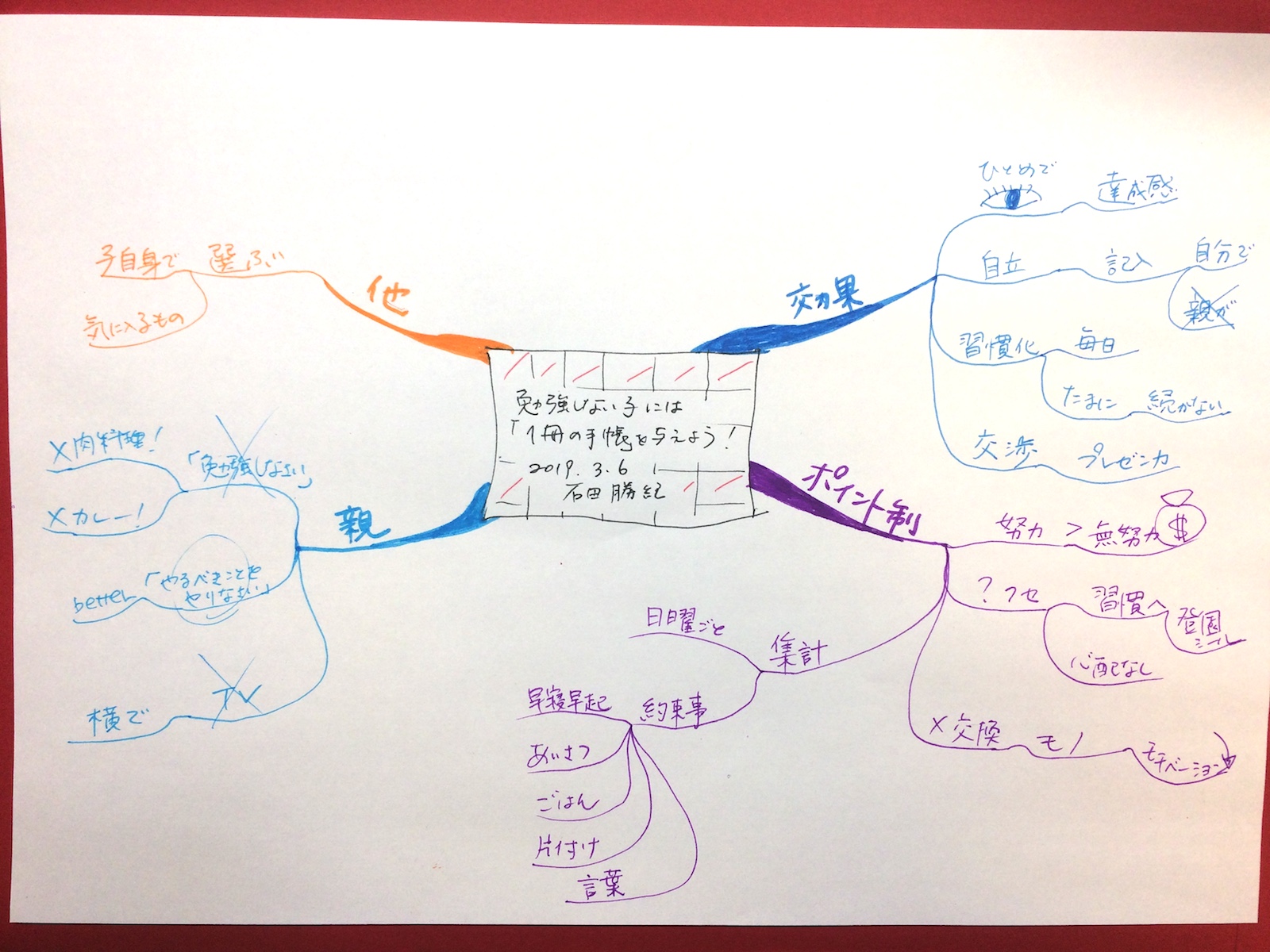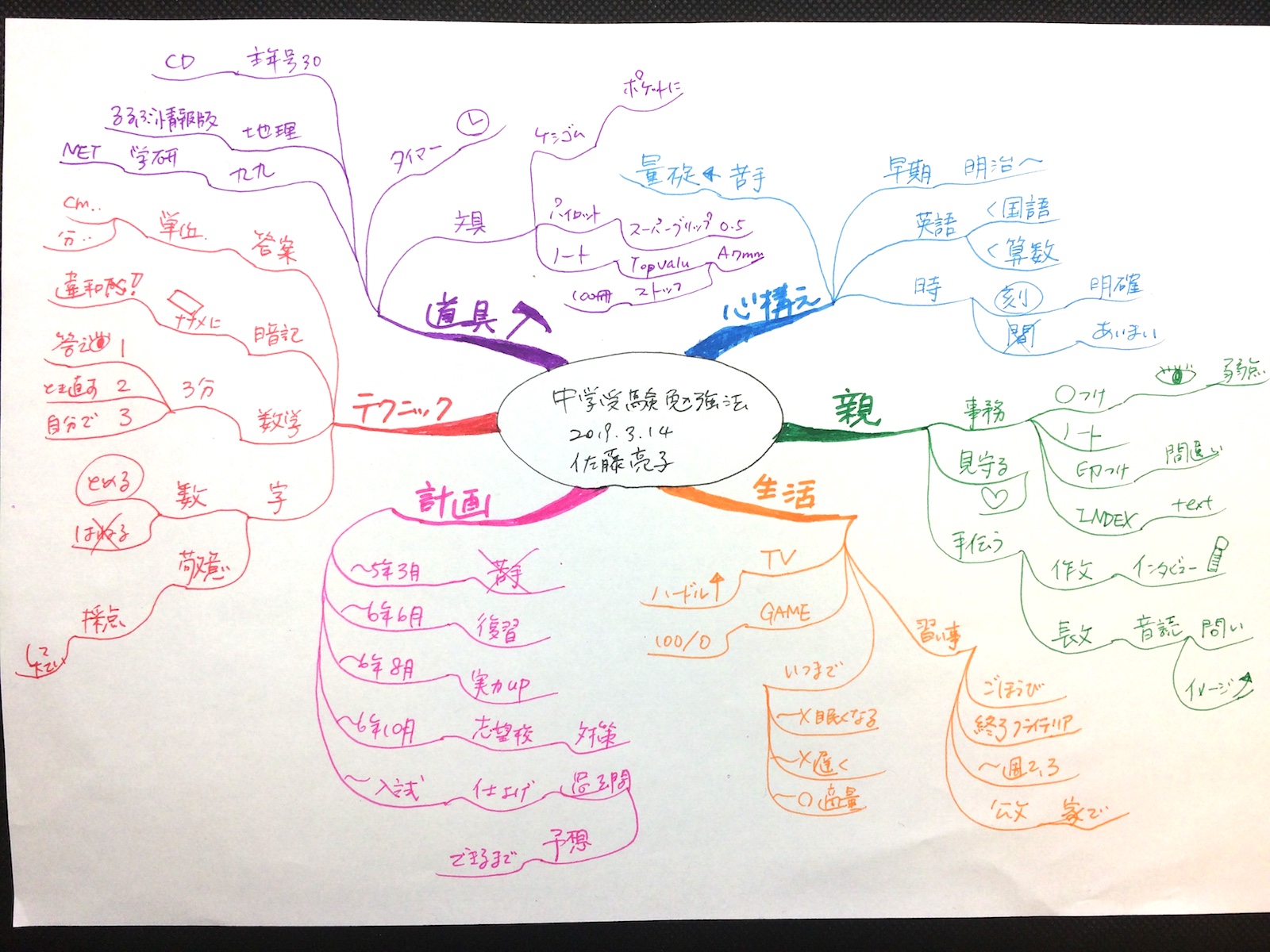PHILOSOPHY FOR 41 YEARS OLD AND OVER
考えることに、手遅れはない。
この世の身近な出来事を深くやさしく考えた、大人のための哲学。
「人とつながりたい」「自分を認めてもらいたい」というのが、ハマる人々の言い分である。しかし、自分を認めルために他人に認めてもらう必要はない。空しい自分が空しいままに、空しい他人とつながって、なんで空しくないことがあるだろうか。人は、他人と出会うよりも先に、まず自分と出会っていなければならないのである。まず自分と確かに出会っているのでなければ、他人と本当に出会うことなどできないのである。
次々に変わってゆく映像は、人に考える暇を与えない。人は、考えるためには、一度は必ず映像を離れる必要がある。一方的に映像を受けとる習慣は、考えるという人間を人間たらしめテイル根幹の部分を、気づかず磨滅させるのである。
「知る」ということと「わかる」ということは違うことだと言うこともできる。たくさんの情報を知っていたところで、それがどういうことなのかわかっているわけではない。何であれ、それか゛どういうことなのかわかるためには、自ら考える以外はない。
言葉は交換価値なのではなくて、価値そのものなのだ。
そも学問とは何であるのかを、あれらの野蛮人たちは理解していたものだろうか。「書を捨てよ、街に出よ」。しかし、書は、読んでから捨てるべきものなのである。読みもしないで街に出はべった野蛮人たちのおかげで、見よ、今の世の中、こんなふうなのである。
学問というものが、本来、役に立たない金にならないのは当然なのである。また、ある意味でそれが閉鎖的に見えるのも、当然なのである。世の中全体が、役に立つこと金になることを価値と信じて走っているところで、なんでそれらが価値なのか、そも世の中とは何なのかを、考えるのだからである。そうと信じ込まれている事柄を疑うことが、その事柄にとって役に立つことであるわけがない。
世の中には、世の中には役に立たないことをする人が必要なのである。そのような人こそが、本当は役に立つのである。「無用の用」、役に立たないことを考える人がいなくなれば、世の中どうなるか、明らかであろう。正しい言葉の人ソクラテスは、なぜ死刑になったか。間違えてはならない。彼は正しい言葉を守るために死刑になったのではない。そうではなくて、すでにして完全に自由だったから、結果として死刑になっただけである。
我々は、毎晩眠るけれども、眠る時はいつだって独りである。二人で並んで眠ろうが、大勢ごっちゃになって眠ろうが、眠る時、眠り込む時には、必ず独りである。隣の人と一緒に眠って、一緒に夢を見るということは、絶対にない。眠るということは、完全に独りきりの、自分だけの出来事なのである。これを敷衍すれば、目覚めている時だって、同じである。人は、目覚めている世界には大勢の人がいるので、大勢の人と共に生きていると思いがちだけれども、そうではない。大勢の人が生きているその世界を見、その世界を生きているのは、どこまでもこの自分でしかない。自分というのは、眠っていようが起きていようが、完全に独りなのである。
肉体ではないところの自分は物質ではないが、自分の存在を信じるか信じないかとは誰も問わないであろう。自分の存在は、科学による証明なんぞぬきで、誰もが頭から認めている。これは我々の大常識である。それなら、なんで死んだ人の存在ばかりが特別扱いされることになるのか、逆に私は不思議である。霊の存在が、なんでそんなに不思議なことなのか。
見えるか見えないかということが、不思議か不思議でないかの境い目であるらしい。それなら、見えるということの方は、なんで不思議なことではないのか。見えるものは何であれ存在するのである。夢ですら、存在しなければ見えないのである。ところで、目は閉じているのに見えているあれの存在を、なぜ人は不思議がることをしないのか。見えない幽霊の存在なんぞより、この方が私にははるかに不思議である。
もし「宗教」というのが、何らかのことを教えるということなら、神社は何も教えていない。じっさい、わが国の古神道には、教義もなければ教祖もない。とくに何を言っているというわけでもない。言っているのは、神々がここにいるという、そのことだけである。神々はここにいる。あとは自分でやれ。
最も当たり前のことこそが、最もわからないことなのだと気がつけば、超常現象なんてものは、存在しなくなるのである。「わからない」すなわち神秘、日常こそが、神秘である。世界が在ること、自分であること、そいつが生きて、そして死ぬこと、これら当たり前のことの全てが、驚くべき神秘の出来事である。日々刻々、この驚くべき神秘を体験しているというのに、なんでわざわざ別のところへ、神秘を体験しに行く必要があろう。空を飛んだだのオバケを見たなんてのは、この絶対的神秘に比べれば、オマケみたいなもんである。
41歳からの哲学
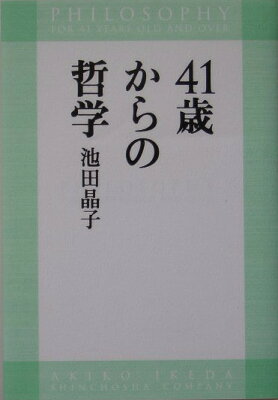 5.その他
5.その他